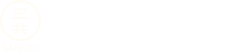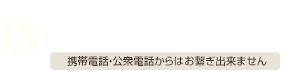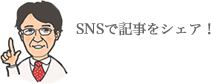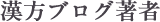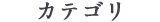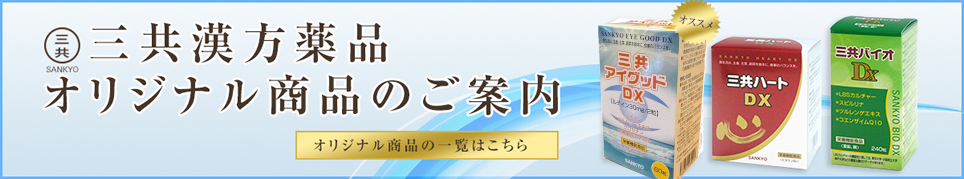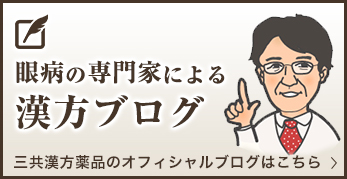AIコラム
漢方に関する情報をAIが紹介します
緑内障と診断されたら?不安を和らげる東洋の知恵と対処法

「緑内障と診断されました」—この言葉を医師から告げられた時、多くの方が不安や恐怖を感じることでしょう。緑内障は日本における中途失明原因の第一位とされており、40歳以上の約5%が罹患しているとも言われています。
しかし、現代医学の治療だけでなく、東洋医学の知恵を取り入れることで、症状の進行を穏やかにし、生活の質を維持できる可能性があることをご存知でしょうか?
漢方医学では、緑内障を「目の気血の巡りの滞り」と捉え、体全体のバランスを整えることで目の健康をサポートする考え方があります。この東洋の知恵は、西洋医学による治療と併用することで、より総合的な健康管理につながります。
本記事では、緑内障と診断された方の不安を和らげ、東洋医学の視点から目の健康を守るための具体的なアプローチ方法をご紹介します。日常生活での改善ポイントから、眼圧コントロールに役立つとされる漢方の知識まで、専門家の見解を交えてわかりやすく解説していきます。
緑内障と向き合いながらも、充実した毎日を送るためのヒントが見つかりますように。
1. 緑内障の不安を和らげる!東洋医学の知恵で見つける新たな希望とは
緑内障と診断された瞬間、多くの方が感じる不安や恐怖は計り知れません。「失明するのでは?」「これからどうなるの?」という疑問が頭をよぎるのは当然のことです。しかし、現代医学の治療法だけでなく、何千年もの歴史を持つ東洋医学にも目を向けることで、新たな希望が見えてくるかもしれません。
東洋医学では緑内障を「気・血・水」のバランスの乱れと捉え、特に肝臓の機能と密接に関連していると考えます。肝は「目の窓」とされ、肝機能の乱れが目の健康に直結するという考え方です。そのため、肝の機能を整えることが緑内障対策の一つとなります。
漢方薬では「釣藤散」や「牛黄清心元」などが眼圧を下げる効果が期待されており、実際に西洋医学と併用している患者さんも少なくありません。京都大学医学部附属病院でも、一部の漢方薬が緑内障患者の補助療法として取り入れられています。
また、鍼灸治療も注目されています。特に目の周りのツボである「晴明」「瞳子髎」「太陽」などへの刺激は、眼の血流を改善し、緊張を和らげる効果が期待できます。これらは東京有名鍼灸院などの専門施設で受けることができます。
さらに、気功や太極拳などの東洋的な運動法も、全身の気の流れを整え、ストレスを軽減させることで間接的に眼の健康をサポートします。特に呼吸法を意識した穏やかな動きは、交感神経を抑制し、結果的に眼圧の安定にも寄与するとされています。
東洋医学の素晴らしい点は、病気を単に「治す」だけでなく、心と体のバランスを整え、生活の質を高める視点を持っていること。緑内障と向き合う長い道のりで、この東洋の知恵を取り入れることは、不安を和らげ、前向きに生きるための大きな支えとなるでしょう。
2. 【医師監修】緑内障と診断された方へ:漢方の力で目の健康をサポートする方法
緑内障と診断されると、多くの患者さんが「失明するのでは」という不安を抱えます。現代医学による治療は欠かせませんが、東洋医学、特に漢方の知恵を取り入れることで、症状の緩和や進行の抑制に役立つ可能性があります。漢方医学では目の健康を全身のバランスと関連付けて考えるため、西洋医学とは異なるアプローチで緑内障をケアできます。
日本東洋医学会認定専門医の田中誠一先生によると、「緑内障は『気・血・水』のバランスの乱れから生じる症状と捉えられます。特に肝の機能低下と関連することが多いため、肝機能を整える漢方薬が処方されることがあります」とのこと。
代表的な処方として挙げられるのが「釣藤散(ちょうとうさん)」です。高血圧や自律神経の乱れを整える効果があり、血流改善を通じて眼圧のコントロールをサポートします。また「牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)」は、特に正常眼圧緑内障の患者さんに使われることがあります。目の血流を改善し、視神経の保護に働きかけるとされています。
漢方薬の服用を検討する際は、必ず眼科医と相談した上で、漢方に詳しい医師の診察を受けることが重要です。ツムラやクラシエなどの製薬会社が製造する医療用漢方製剤は、保険適用で処方されることもあります。
漢方の考え方では、食事や生活習慣も重視します。緑内障の方には、肝機能を高める食材(緑黄色野菜、クコの実など)や、血流を改善する食材(生姜、にんにく)がおすすめです。また、目の周りのツボ押しも効果的とされています。特に「睛明」「攅竹」「太陽」などのツボを優しく刺激することで、目の疲れや緊張を和らげる効果が期待できます。
東洋医学の知恵を取り入れることで、緑内障と上手に付き合っていくための新たな視点が得られるかもしれません。ただし、漢方は西洋医学の治療の代替ではなく、補完的な役割として活用することが大切です。定期的な眼科検診と処方された点眼薬の使用を継続しながら、漢方の力も借りて目の健康を守りましょう。
3. 緑内障の進行を穏やかに:東洋医学が教える日常生活の改善ポイントとセルフケア
東洋医学の視点から見ると、緑内障は単なる眼圧上昇だけでなく、全身のバランスの乱れが関係していると考えられています。中医学では「肝」のエネルギーの滞りが目の健康に影響すると捉え、日常生活の中で実践できる工夫が数多く存在します。
まず食生活においては、抗酸化作用の高い緑黄色野菜を積極的に摂取することが推奨されます。特に人参やほうれん草、ブロッコリーに含まれるルテインやゼアキサンチンは網膜保護に効果的です。また、ブルーベリーやビルベリーに含まれるアントシアニンも視神経保護に役立ちます。
東洋医学では「経絡」と呼ばれるエネルギーの通り道を整えることも重視します。目の周りには「膀胱経」や「胆経」が通っており、これらのツボを刺激することで目の健康維持に役立つとされています。例えば、目の内側にある「睛明」や、こめかみ付近の「太陽」などのツボを、朝晩やわらかく押すだけでも効果が期待できます。
日本の鍼灸院や漢方クリニックでは、西洋医学的治療と並行して、こうした東洋医学的アプローチを提供しているところもあります。
目の疲労を軽減するための実践として、20分のパソコン作業ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)先を見る「20-20-20ルール」も有効です。また、朝起きてすぐに白湯を飲むことで代謝を上げ、体内の水分バランスを整えることも東洋医学では推奨されています。
ストレス管理も重要なポイントです。太極拳や気功、瞑想などの東洋の伝統的な運動法は、全身の気の流れを整え、交感神経の過剰な緊張を緩和します。特に「八段錦」という気功法には目の健康に効果的な動きが含まれています。
就寝前のホットアイマスクや蒸しタオルでの目の温罨法も、血行を促進し目の緊張をほぐすのに役立ちます。東洋医学では「冷え」が様々な不調の原因になると考えるため、目を温めることは理にかなっています。
緑内障の進行を穏やかにするためには、西洋医学的な治療をしっかり受けながらも、こうした東洋の知恵を日常に取り入れることで、より総合的なケアが可能になります。心と体のバランスを整え、目だけでなく全身の健康を維持していくことが、長い目で見た緑内障との共生の道なのです。
白内障、飛蚊症、緑内障、黄斑変性症、網膜剥離などでお悩みの方に最適な漢方をおすすめします。
フリーダイヤル 0120-4976-01 / 携帯・公衆電話 072-250-7708
受付時間 平日9:00~18:00 /メールでのお問い合わせはこちら
- 2025.12.29見逃せない白内障の警告サイン!原因を知って賢く対策する方法
- 2025.12.27眼圧が高いと言われたら…緑内障予防に役立つ東洋医学の知恵
- 2025.12.24年齢とともに増える飛蚊症|自然療法で目のトラブルに立ち向かう
- 2025.12.22白内障は生活習慣病?知られざる原因と今日から始める予防法
- 2025.12.20緑内障患者が実感!生活の質を改善した自然療法とは
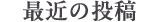
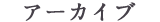
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (5)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (7)
- 2025年6月 (4)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (1)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (7)
- 2024年10月 (5)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (6)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (9)
- 2024年2月 (11)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (6)
- 2023年10月 (1)
- 2023年8月 (8)
- 2023年7月 (14)
- 2023年6月 (10)
- 2023年5月 (7)
- 2023年4月 (6)